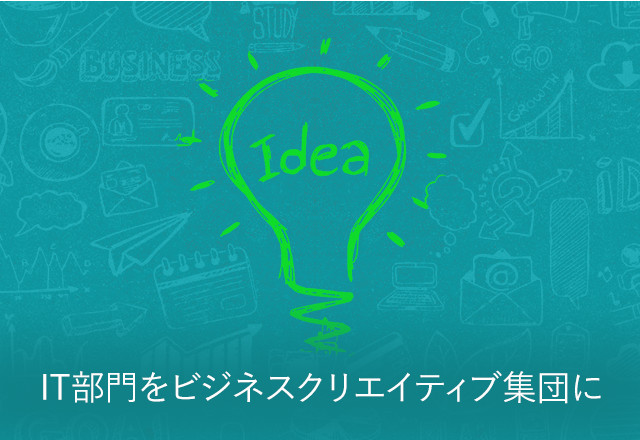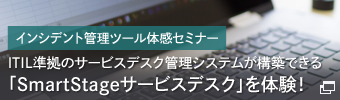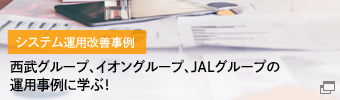- Tips
2025.10.07
更新日:
2025.10.07
全2回 「経営のパートナー」へ! IT部門が知っておきたい経営戦略用語17選 《連載:第1回》 IT部門が知っておきたい経営戦略用語【超基礎編】
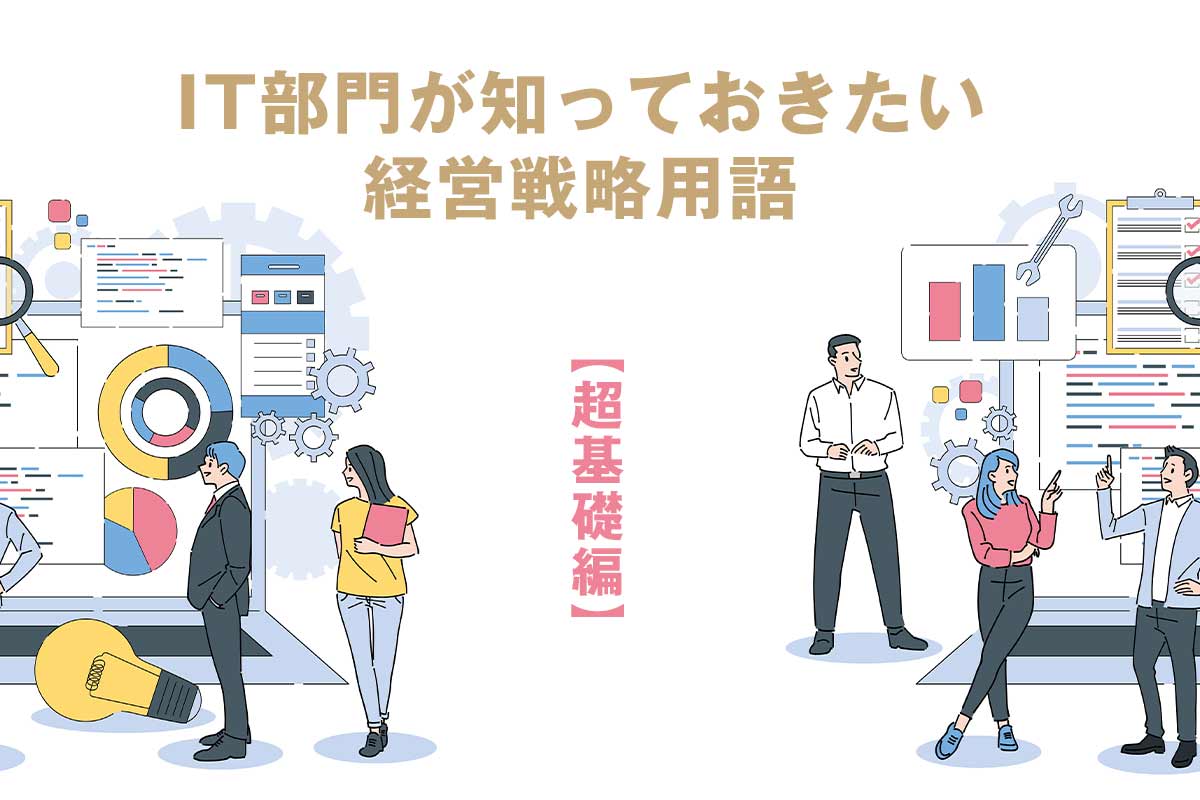
現在、多くの企業が、IT部門に“ITのスペシャリスト”だけでなく、“経営のパートナー”としての役割を期待しています。そのため、今後はシステムの保守・運用や開発の担当者であっても、ビジネスや経営の知識を求められる場面がますます増えていくはずです。
とりわけ経営サイドと同じ、あるいはそれに近い目線でコミュニケーションを図るためには、経営戦略の基本的な理解が欠かせません。そこで今回の記事では、その第一歩として、最低限押さえておきたい基本的な経営戦略用語を17個ピックアップして解説します。
〈1〉ドメイン
同じ言葉でも、IT分野と経営戦略の分野では意味合いが異なるケースがありますが、「ドメイン」もそのひとつです。IT分野で「ドメイン」と言えば、一般的には“インターネット上の住所”を指します。たとえばWebサイトのURLが「https://○○○.com」であれば、「○○○.com」の部分がドメインに該当します。
一方、経営戦略においてドメインは、企業や事業の「活動領域」及び「競争領域」といった意味で使われます。通常、「誰に」「何を」「どのように提供していくのか」の3軸で構成され、単に既存の活動領域を定義するのではなく、将来的な方向性やあるべき姿を示す戦略的な枠組みであることが求められます。
〈2〉バッファ
バッファも、ITと経営戦略の分野で意味合いが異なる言葉のひとつです。もともと英語(buffer)では“緩衝するもの”“緩衝材”などを意味します。IT分野では、複数の機器間でデータのやりとりをする際、処理速度の差を緩和するために一時的にデータを蓄える記憶領域をバッファと呼びます。
経営やビジネスにおいてバッファは、予算やスケジュール、人員、在庫などに設ける“余裕”や“ゆとり”を指すのが一般的です。適切にバッファを確保しておくことで、不測の事態に柔軟に対応でき、プロジェクトや事業を安定的に進めることができます。
〈3〉コア・コンピタンス
「コア・コンピタンス」とは、企業が長期的に競争優位を築くための「核となる能力」や「独自の強み」を指す概念です。ただし、ある能力や強みがコア・コンピタンスと見なされるためには、次のような条件を満たす必要があるとされています。
・最終的な製品・サービスを通じて顧客に利益(価値)をもたらすこと
・複数の市場や製品に応用できること
・競合他社が容易には模倣できないこと
具体例としては、ソニーがポータブルオーディオプレイヤー『ウォークマン』を生み出した背景にある小型化技術や、トヨタ自動車の独自の生産方式として知られる「トヨタ生産方式」などが挙げられます。これらの強みに経営資源を集中させる経営手法を「コア・コンピタンス経営」と呼びます。
〈4〉KSF
KSFは”Key Success Factor”の略称で、日本語では「重要成功要因」と訳されます。文字通り、「事業を成功に導くために欠かせない要素」を意味し、具体的にはKGI(重要目標達成指標)を実現するために特に注力すべき課題や条件を指します。
KSFの達成状況を定量的に測定するために設定されるのがKPI(重要業績評価指標)です。たとえばKSFが「顧客満足度の向上」であれば、「顧客アンケートにおける満足度スコア平均90%以上」といったKPIを設けることで、取り組みの進捗を評価できます。

なお、KSFと同じ意味合いで、CSF(Critical Success Factor)という言葉が代わりに用いられることあります。
〈5〉ブルーオーシャン戦略
ブルーオーシャン戦略とは、競争の激しい既存市場(レッドオーシャン)を避け、競合のいない新たな市場(ブルーオーシャン)を自ら創り出すことで、“差別化”と“低コスト”の両立を追求する経営戦略です。「戦わずして勝つ」ことを目指すアプローチとも言えます。
この戦略のポイントは、既存市場では十分に満たされていないニーズを持つ「非顧客層」に着目し、新たな価値を提供することにあります。日本企業における代表的な成功事例としては、ゲームに馴染みの薄い幅広い層をユーザーとして取り込み、新たな市場を切り拓いた任天堂株式会社の『Wii』が挙げられます。
〈6〉同質化戦略
同質化戦略とは、市場のリーダー企業が豊富な経営資源を活用して、2番手・3番手のチャレンジャー企業が仕掛ける差別化戦略を無効化するために用いる戦略です。典型的な例としては、大手飲料メーカーが、他社がヒットさせたドリンクと同じジャンルの商品を後発で投入するケースが挙げられます。
同質化戦略の手法には大きく分けて2種類あります。ひとつは、チャレンジャー企業の製品・サービスをほぼそのまま模倣する方法、もうひとつは、それらの製品・サービスに改善や改良を加えて提供する方法です。こうした戦略に対し、経営資源で劣るチャレンジャー企業は、リーダー企業が容易に同質化できない、あるいは同質化するメリットが乏しい戦略を検討する必要があります。
〈7〉ニッチ戦略
ニッチ戦略は、大手企業がターゲットとしない、あるいは参入しにくい小規模な市場に経営資源を集中し、トップを目指す戦略です。ブルーオーシャン戦略が「これまで存在しない新市場の創出」を目指すのに対し、ニッチ戦略は「既存市場の中で特定のニーズを持つセグメントに特化」する点が特徴です。
ニッチ戦略のメリットとしては、限られたリソースしか持たない中小規模の企業でも競争優位性を確保しやすいこと、独自のポジションを築くことでブランドロイヤリティを高めやすいことなどが挙げられます。代表的な事例として、保険業界において中小企業に特化した独自のビジネスモデルを構築している大同生命保険株式会社が知られています。
〈8〉M&A
M&Aは「Mergers and Acquisitions(合併と買収)」の略語で、企業同士の合併や、株式を通じた買収などを意味します。主な手法には「合併」「会社分割」「株式譲渡」「事業譲渡」の4種類があり、実施目的は新規市場への参入、経営規模の拡大、組織再編、さらには経営不振に陥った企業の救済など、多岐にわたります。
M&Aによるメリットは、売り手と買い手で異なります。売り手側は、売却益の獲得や従業員の雇用維持などが期待できます。一方、買い手にとっては、自社にない技術やノウハウ、販路の獲得による事業多角化の実現や、既存事業の拡大や効率化・コスト削減、後継者問題の解消などが挙げられます。
〈9〉アライアンス
アライアンスとは、複数の企業や組織が共通の目的を達成するために協力関係を築く、戦略的な取り組みです。M&Aのように企業統合を伴うことなく、それぞれが独立性を保ちながら連携する点が特徴です。そのため、M&Aよりもリスクを抑えつつ、自社単独では難しい技術、市場、顧客層へのアクセスが可能になるというメリットがあります。
アライアンスの形態としては、業務提携や販売提携、資本提携のほか、大学や研究機関、スタートアップと協働するオープンイノベーションなどが挙げられます。例えば、ECサイトを運営する企業同士が販売提携を結べば顧客層の相互拡大につながり、さらに実店舗を持つ企業と連携すれば販路拡大の効果も期待できます。特に近年では、オープンイノベーションがDX推進における重要な手法とされており、今後の拡大が予想されます。
〈10〉範囲の経済
範囲の経済(Economies of Scope)は、ひとつの企業が複数の事業や製品を展開することで、事業ごとのコスト削減や業務効率化が実現される現象を指します。技術やノウハウ、販売チャネル、物流システム、ブランド力などの既存の経営資源を共有できることから生まれる効果であり、事業多角化の重要なメリットとされています。
国内企業の代表例としては、写真フィルム事業で培った技術を応用し、化粧品や医療品事業を展開している富士フイルムが知られています。また、共通の技術基盤を活かして複数のサービスを展開するプラットフォームビジネスも範囲の経済性を活用したビジネスモデルの一例です。
なお、混同されやすい言葉に「規模の経済(Economies of Scale)」がありますが、こちらは「単一の製品を大量に生産することで製品1つあたりのコストを低減する効果」を指します。
次回の第2回目記事では、戦略立案などの実践にも役立つフレームワークを7つ紹介します。