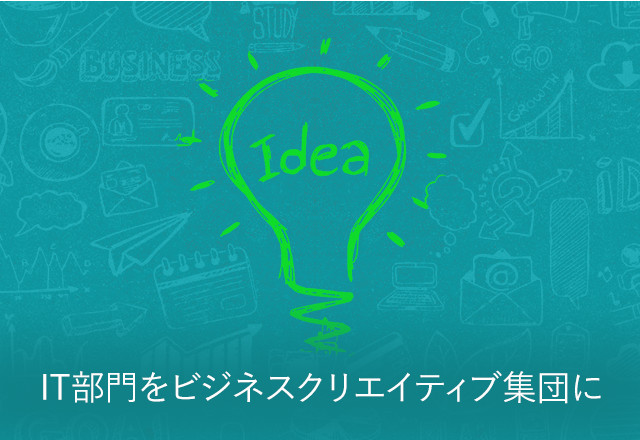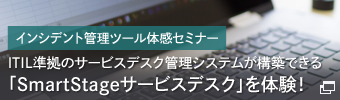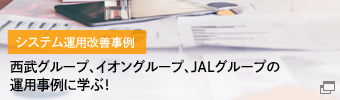- Tips
2025.05.28
更新日:
2025.05.20
全2回 “ITのお守り役”から“経営・事業のパートナー”へ——IT部門を変える「企画力」 《連載:第2回》 IT部門の企画立案・プレゼン資料作成に役立つ実践ノウハウ
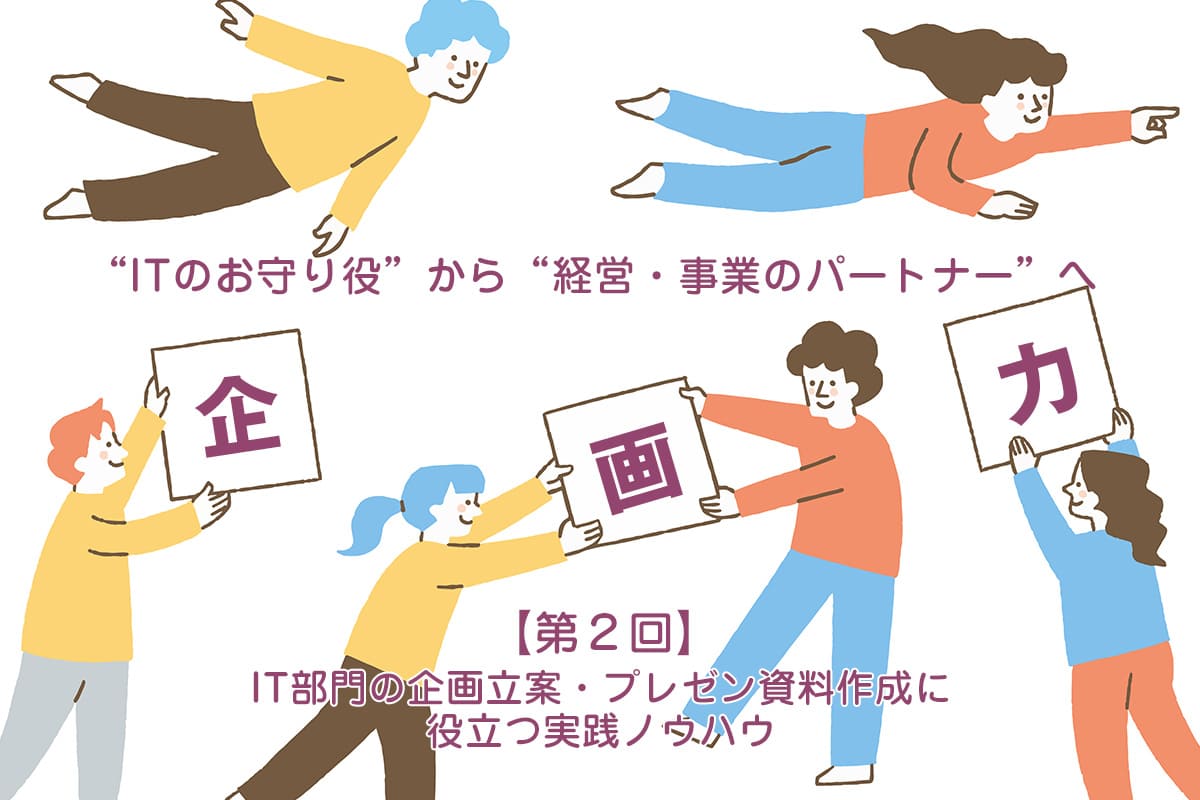
IT部門が“IT・デジタル推進の旗振り役”、さらに“経営・事業の戦略的パートナー”へと変わってくために欠かせないスキルが「企画力」。一口に企画と言ってもその種類は多岐にわたりますが、いわゆる「良い」企画、課題解決につながる企画を考えるうえで不可欠なポイントは共通しています。それが次の2つです。
(1)ターゲットユーザーを理解する
(2)ゴール(目的)を明確化する
“IT・デジタル推進の旗振り役”として、または経営方針に基づいたIT戦略を構想・実行できる“経営・事業の戦略的パートナー”として、企業の競争力強化に寄与する役割です。
ここでは社内向けのシステム開発を例に挙げて、それぞれのポイントを解説します。
(1)ターゲットユーザーを理解する
ここで言う「理解」とは、「本当の課題やニーズを把握すること」を意味します。「本当の」というのは、ターゲットユーザー(社内システム開発の場合はユーザー部門)の声や要望をそのまま機能に反映しても、結果的に課題解決につながらない、ということが多々あるからです。
多忙や業務プロセスの複雑さなど、さまざまな理由により、当事者自身が本質的な課題に気付いていないケースや、明確に言語化できないケースは少なくありません。
企画者に求められるのは、「本当の課題やニーズは、ユーザーから“与えられる”ものではなく、企画者が“発見”または“引き出す”もの」という視点。ヒアリングをおこなう際は、ユーザーの要望にとらわれず、その背景にある「本当に成し遂げたいことや困っていること」に焦点を当てて深堀りすることが重要です。
なお、ターゲットユーザーの顔が見えにくいto C(一般消費者向け)またはto B(法人向け)のサービス開発の場合は、詳細なペルソナ(年齢や性別、ライフスタイル、価値観などを具体的に設定した架空のユーザー像)を作成し、課題やニーズを明確にする手法が一般的です。
(2)ゴールを明確化する
企画におけるゴールとは、それを実行することで最終的に達成したい目標や成果のことです。特に社内向けのシステム開発では、「システムを作ること自体」が目的化してしまい、導入後に全く使われないといったケースも少なくありません。
こうした手段の目的化を防ぐためにも、企画フェーズの段階で目標を明確に定め、関係者と共有しておくことが重要です。最適な目標は企画内容に応じて異なりますが、「具体的であること」は必須条件。とりわけ、新規顧客獲得数やリピート率、工数の削減率、顧客満足度(NPSスコア)のような、数値で測定できる指標を設定すると、企画実施後の効果検証や改善にも役立ちます。
社外向けサービスの場合は、こうした企業側のゴールだけでなく、ユーザー側のゴール設定も欠かせません。ユーザーがその「サービスを利用する理由」や「期待する成果」を明確にし、そこから逆算して機能や仕様を考えることで、ユーザー視点に立ったサービス設計が可能になるからです。
企画立案の第一歩です。なお、一旦企画が完成した際には、次のような観点で全体を見直してみるのが効果的です。
このように、ターゲットユーザーの課題・ニーズと、達成すべきゴールを明確にしたうえで企画を立てていくことが、企画立案の第一歩です。なお、一旦企画が完成した際には、次のような観点で全体を見直してみるのが効果的です。
・ユーザーが本当に解決したいと思っている課題に焦点を当てているか?
・本当にユーザーの課題を解決する提案か(本当にユーザーにとってメリットがあるか)?
・(社外向けサービスの場合)ユーザーが対価を払う価値のある解決策か?
プレゼン資料に欠かせない3つの工夫
いくら良い企画を考えても、実行しなければ意味がありません。そのために避けて通れないのが、企画書や提案書を含むプレゼン資料の作成です。
プレゼン資料の目的は、上司やステークホルダーから承認を得ること。そのためには、単に体裁の整った資料ではなく、「読み手・受け手の興味を引き、納得させる」資料を作成する必要があります。つまり、企画書作りには「採用される」ための伝える工夫や戦略が欠かせないということです。
とりわけ大切なのが次の3つのポイントです。
(1)タイトルで興味を引く
興味を引くためには、タイトルから工夫が必要です。例えば、「〇〇〇〇の導入について」といった一般的で無難なタイトルよりも、「生産性を〇〇%向上!」「年間〇〇時間の工数削減を実現する~~」のような、具体的なメリットや目標を前面に打ち出すことで、より注目を集めやすくなります。
(2)資料は端的にまとめる
資料の枚数が少なくなるように、できるだけ端的にまとめる工夫も重要です。読み手や意思決定者のムダな負担を減らすという狙いもありますが、量が多いと「要点が整理できていない」「自信がない」というマイナスイメージを与えてしまう恐れもあるからです。提案内容の裏付けに大量のデータが必要な際は、要点を1~数枚にまとめ、データは補足資料として別途提出するという方法を検討するのも良いでしょう。
(3)共感を呼ぶ構成で伝える
料の内容については、単に企画をわかりやすく説明するだけでは不十分です。最終的に意思決定者に納得して承認してもらうためには、自分事化してもらえるくらい“共感”を醸成しながら伝えていくことが大切です。そのために有効なのが、次のようなストーリー構成です。
1.課題
ターゲットユーザーが抱えている具体的な課題を提示します。
2.原因
その課題が発生している根本的な原因を示します(複数ある場合は特に重要なものに絞る)。
3.解決策
課題をどのように解決するか、具体的な施策やシステムを提案します。費用やスケジュールの目安もここで示すことが必要です。
4.効果・メリット
解決策を実行した結果、どのような成果が期待できるかを説明します。
さらに、4つのステップそれぞれに裏付けとなるデータを提示することで、企画全体の信頼感と説得力が高まります。
今回は、企画立案やプレゼン資料の作成に役立つ基礎的かつ実践的なノウハウをご紹介してきました。ただし、企画力は他のビジネススキルと同様に、一朝一夕に習得できるようなものではありません。やはり大切なのは経験です。
企画の経験があまりない場合は、まずは小さな提案から始めて、少しずつ成功体験を積み重ねていくのが良いでしょう。時間はかかるかもしれませんが、その過程での試行錯誤やチャレンジが、やがてIT部門の体質や風土を変え、最終的にはDXのような全社的な取り組みの中で成果として実を結ぶはずです。