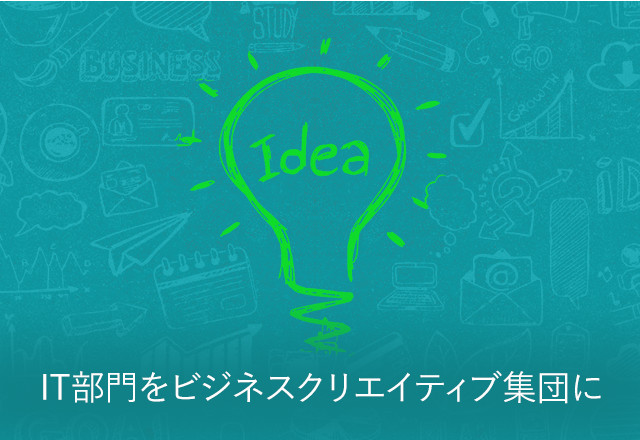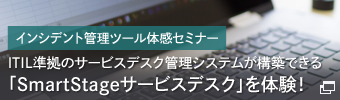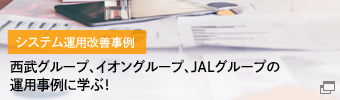- Tips
2025.03.18
更新日:
2025.03.18
全2回 DX時代のIT部門に必須!業務改善を成功に導く2つのフレームワーク 《連載:第2回》 効果的な業務改善アイデアを引き出す「ECRS」
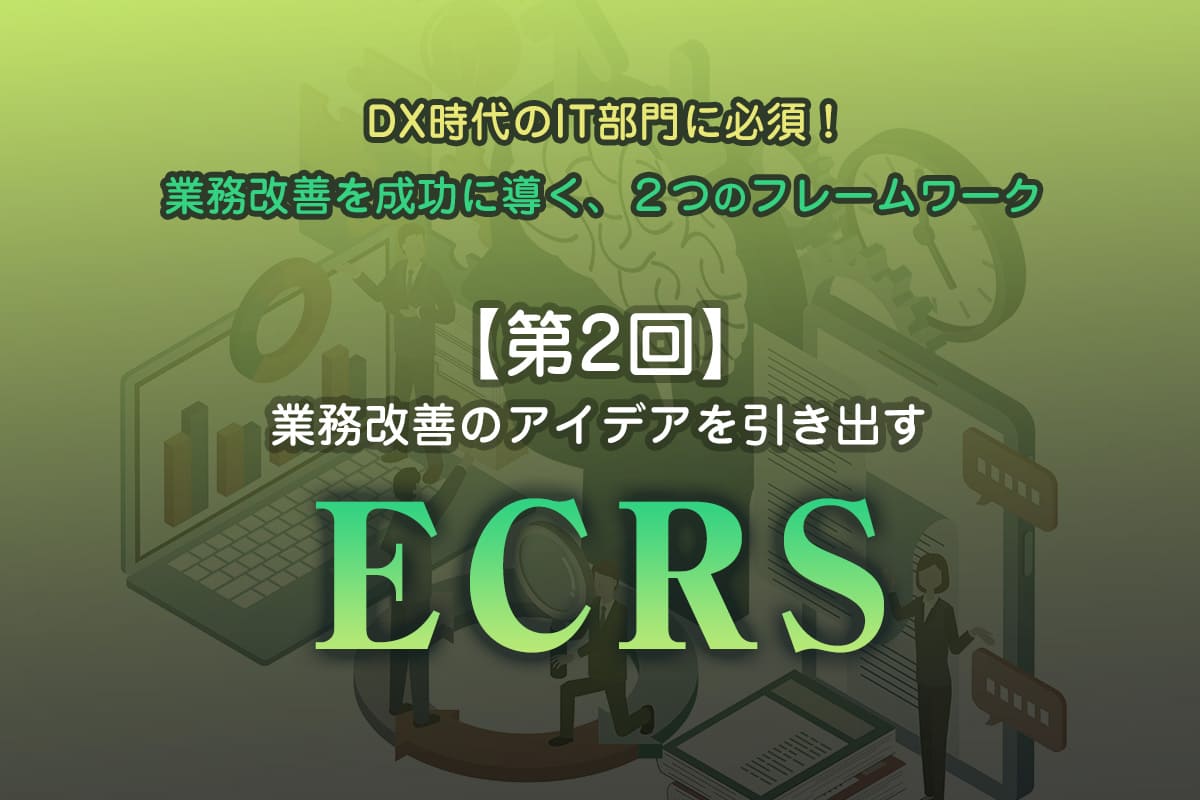
前回は業務改善の最初のステップである現状把握・分析に効果的な「BPMN」という業務フロー図の表記法を紹介しました。今回は、そのBPMNで抽出した課題の改善策を検討・策定する際に役立つフレームワーク「ECRS」について解説します。
ECRSの4つの視点
ECRS(イクルス)は業務プロセスの課題を4つの視点(切り口)から改善するフレームワークです。別名「改善の4原則」とも呼ばれており、もともとは製造業の生産管理を効率化するために考案されたノウハウですが、現在は業界・業種問わずさまざまな領域で活用されています。
ECRSを活用するメリットの1つは、改善策のアイデアを発想しやすくなること。それぞれの視点が思考の方向性を明確にしてくれるので、ポイントを押さえた的確なアクションにつながります。

ECRSの4つの視点
それぞれの視点について見ていきましょう。
・Eliminate(排除する)
「不要な作業や工程を無くせないか?」という視点で改善策を検討します。ここで言う「不要」とは、理由や目的が不明であるにもかかわらず習慣のように続いているタスクなど。例えば以下のような改善策が該当します。
・必要性の低い上長確認や報告書の作成を廃止する
・ミーティングは議題と関係のあるメンバーだけが参加者する
・Combine(結合する)
「複数の業務を一緒に(一本化)できないか?」「並行して進められないか?」という視点で改善策を検討します。具体的には以下のような改善策が挙げられます。
・複数の担当者が分担していた発注業務を1人が担当する
・関係者に個別にメールを送るのではなくグループチャットに一括送信する
・Rearrange(入れ替える)
「業務の順序や場所、担当者を変更することで効率化できないか?」という視点で改善策を検討します。以下のような改善案が当てはまります。
・上長確認のタイミングを前倒しする
・ルーティン業務の一部をアウトソーシング化する
・Simplify(簡素化する)
「作業をもっと簡単にできないか?」という視点で改善策を検討します。以下のような、ITツールによる自動化・省人化などの解決策が該当します。
・システムへの入力作業をRPA(ロボティック・プロセス・オートメーション)で自動化する
・毎回担当者が白紙から作成している資料をテンプレート化する
ECRS活用のポイントと改善事例
ECRSを活用するもう1つのメリットとして、改善すべき課題の優先順位が明確になるという点が挙げられます。上述の4つの視点は改善効果の高い順に並んでいるため、「E(排除)」→「C(結合)」→「R(代替)」→「S(単純化)」の順に業務を見直していくことで、余計な手間やコストをかけずに大きな改善効果が期待できる仕組みになっているのです。
具体的には、まず「E」の視点で改善案を検討し、実現が難しい場合は「C」、それも無理なら「R」……という流れで進めていくイメージです。また、ECRSという言葉が覚えにくい場合は、代わりに「な・い・じゅ・か」(「無くせないか?」「一緒にできないか?」「順序を変えられないか?」「簡単にできないか?」の頭文字を合わせた造語)と日本語で覚える方法もあります。
改善策を策定した後は、スケジュールを立て、施策の実行に移ります。その際に忘れてはいけないのが、定量・定性効果の定期的な評価と施策の見直しです。最適な効果指標は改善対象の業務によって異なりますが、例えば定量効果を測る指標としては、業務時間や残業時間、コストなどの削減数(率)などが多く用いられています。
参考のために事例を挙げておくと、例えばある国立大学では、生産性向上のためにECRSを用いた業務削減・効率化を実施し、合計で約6,300時間の業務削減を実現しています。また、ある大手製薬会社では、数十年稼働してきたレガシーシステム(メインフレーム)を刷新する際にECRSを活用し、複雑化した基幹系システムのスリム化を図るべくECRSに沿って検討を進めた結果、100以上存在したシステムを 約7割減らし、約3億円/年の運用コスト削減に成功しているということです。
業務改善は地味な作業が多く、成果を出すには根気強さが必要ですが、トヨタ自動車株式会社の「カイゼン」を例に出すまでもなく、企業の競争力向上に欠かせない取り組みであることは言うまでもありません。 前回の冒頭ではIT部門の業務を改善するメリットしか触れられませんでしたが、ビジネスサイドの業務改善を実現すれば顧客満足度の向上につながるケースもありますし、今回紹介したフレームワークを知っておくことで、他部門の業務改善プロジェクトにこれまで以上に貢献できるようになるはずです。
なお、『SmartStage』では他にもIT部門が知っておきたい他ジャンルの知識を紹介しています。是非以下の記事も業務にお役立てください。
いまIT担当者が知っておきたいマーケティング知識|SmartStage
もはや常識! DX時代のIT部門が押さえておきたい会計知識(基礎編)|SmartStage