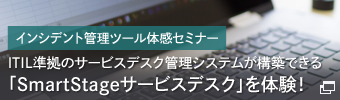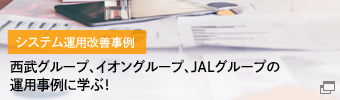![]() コラム
コラム
根本原因分析(RCA)とは? 実践の流れや代表的な手法を解説

目次
-
問題が発生した際に再発を防ぐには、根本原因の特定が欠かせません。その際に用いられるプロセスとして注目されているのが、根本原因分析(RCA)です。根本原因分析では、具体的にどのような手法を用いて、問題解決を目指すのでしょうか。
本記事では根本原因分析の概要や注目される理由、問題を解決するまでの流れ、代表的な手法などを解説します。問題の原因を特定し、解決策の検討に役立つ根本原因分析ですが、正しく実施しなければ、期待する効果が得られない可能性もあります。ぜひ本記事を参考にして、問題の発生を未然に防げる仕組みづくりにお役立てください。
この記事で分かること
・根本原因分析(RCA)の定義と目的
・根本原因分析(RCA)を問題解決につなげる方法
・根本原因分析(RCA)を実践する上でのポイント -
根本原因分析(RCA)とは?

根本原因分析(RCA)とは、組織やシステム、プロジェクトなどでトラブルが発生した際に、その根本となる原因を特定する手法もしくはプロセスを指します。RCAはRoot Cause Analysisの略称です。
トラブルが発生した際に適切な対処をするためには、その根本原因を探さなければなりません。また、根本原因が分かれば、再発を防ぐための対策を講じることもできます。
根本原因分析は、問題の本質的な原因を明確にすることで、問題の早期解決につなげ、再発を防ぐために重要なプロセスです。トラブルの発生を未然に防ぐことで、組織力の強化やシステムの品質向上などの効果が期待できます。根本原因と直接原因
トラブルの原因は、大きく分けて「根本原因」と「直接原因」の2つがあります。
根本原因とは、トラブルの発生に至る本質的な原因を指します。一方、直接原因は、トラブルを引き起こす直接的なきっかけとなるものです。
例えば、納期の誤認によって、遅延が発生したケースを考えてみましょう。この場合の直接原因は「担当者が納期を勘違いしていたこと」です。しかしその背景には「納期管理の仕組みが構築されていなかった」「仕組みはあるものの適切な運用がされていなかった」といった根本原因があると考えられます。
トラブルが発生した際にこの根本原因を特定することで、表面的な対応にとどまらず、再発を未然に防ぐための本質的な対策につなげることが可能です。 -
根本原因分析(RCA)が注目される理由

近年根本原因分析(RCA)が注目されている理由の一つは、さまざまな業界でITツールやシステムの導入が進み、ビジネス環境がこれまでよりも複雑になっていることです。
どのような業界でも、トラブルの発生は業務の進行を遅らせる要因となります。しかし、ビジネス環境が複雑化するにつれ、トラブルの因果関係も同様に複雑化しており、従来の手法では原因の特定に時間がかかってしまうケースが多いです。
根本原因分析は、複雑に絡み合った因果関係を体系的に整理し、本質的な原因を特定することで、効率良くトラブルへの対応や再発防止策を講じることができます。
また業務が長期的に滞るリスクを軽減できることも、根本原因分析が注目されている理由の一つです。早期にトラブルの根本原因を突き止め、素早い対応を取ることができれば、ダウンタイムが長引くことによる損失を防げるでしょう。 -
根本原因分析(RCA)を用いて問題を解決するまでの流れ
では、根本原因分析(RCA)で問題を解決するには、どのような流れで進めていけばいいのでしょうか。解決までの5ステップを、順を追って解説します。
1. 解決すべき問題を定義する
まず、根本原因分析によって解決すべき問題を明確に定義します。解決すべき問題が曖昧なままでは、正確な分析が行えず、適切な対応が取れません。
抽象的に発生した問題を定義するのではなく、詳細を具体的に定義すると、その後の分析が行いやすくなります。解決すべき問題がいくつかある場合、効率的に問題を解決するには、それぞれの問題を定義し、一つずつ根本原因分析を行うことがポイントです。
また、問題の分析に関わる全てのメンバーが、問題について共通の認識を持つことも重要になります。例えば、納期管理に問題があるとしても、メンバー全員が管理体制への課題を感じているわけではありません。主観的な定義ではなく、実際のデータなどに基づいた具体的かつ測定可能な定義を行い、周知することで、全てのメンバーが共通認識を持つことができます。
加えて、アラートによる監視を行い「どのような兆候が見られたら問題の発生と見なすか」も定義しておくと良いでしょう。問題発生の兆候に気付く仕組みづくりをしておけば、問題の発生を未然に防げる上、再発防止にも役立ちます。2. 必要なデータを収集する
解決すべき問題が明確に定義できたら、問題があることを裏付けるために、必要なデータを収集しましょう。対象となるのは、以下のようなデータです。
・システムログ
・アプリの動作状況に関するデータ
・ユーザーからのフィードバック
・インシデントレポート
・関連データソースのレビュー
上記のデータを収集する際は、問題に関して以下のようなポイントを考慮することも重要です。
・発生・判明した時期
・発生している期間
・発生頻度
・判明した理由
・発生によって影響を受ける人物
・主な症状・状況
・発生による短期的・長期的な影響
併せて社内でのヒアリングや状況確認を行うことも、問題の詳細を正確に把握するために役立ちます。3. 根本原因を分析する
必要なデータを収集したら、次は根本原因の分析に進みます。
分析手法には、5why分析やフィッシュボーンチャートなどさまざまなものがあります。それぞれ得意とする視点や用途が異なるため、問題の性質や状況に応じて適切な手法を選ぶことが重要です。代表的な手法は後ほど詳しく解説します。
原因を分析する際は、先入観を持たず多角的に検討し、根本原因となり得る複数の候補を洗い出すことが大切です。その上で、以下の観点から慎重に絞り込んでいきましょう。
・各候補に共通する特徴や傾向はあるか
・各候補がどの程度深刻な影響を及ぼすか
・候補ごとの影響が業務や顧客に対してどのように現れるか
・各原因を完全に取り除くことが現実的かどうか
まず、原因候補の共通点を探ることで、問題全体の構造や傾向をつかみます。次に、それぞれの深刻度や影響度、解消可能性を総合的に評価し、最も本質的な原因を特定するのが一般的な進め方です。
状況によっては複数の根本原因が関係している場合もあるので、絞り過ぎないよう注意が必要です。4. 対応策を検討し実践する
根本原因が特定できたら、対応策を検討して実践します。
対応策は、その場に対処する短期的なものだけでなく、再発防止に役立つ長期的なものも策定するのが効果的です。一概にはいえませんが、短期的な対策は1週間程度で取り組めるもの、長期的な対策はそれ以上の期間を要するもので分類されるケースが多いです。
以下の項目を明確にし、具体的な対応策を検討しましょう。
・実施方法
・実施における障害・懸念点
・実施にかかる期間
・実施する人物
・実施により生じる可能性がある問題
対応策の案が作成できたら、問題に関係する全てのメンバーに対応策を共有し、実行に移します。プロジェクト管理ツールなどを使用すると、スムーズな共有が可能です。
対応策の実施には数週間を要する場合もあり、内容によってはプロジェクトの進行スケジュールや中間目標などに影響を与える恐れもあります。ガントチャートを活用して進捗状況を「見える化」することで、状況に応じた柔軟な対応や調整を行うことができます。5. 問題解決までの流れを記録する
ここまでの手順で問題を解決できたら、一連の流れを記録として残しておきましょう。
一連の流れを文書化して記録し、誰もが閲覧できる状態にしておくことは、再発を防ぐ上で効果的です。実践した解決策の改善点、解決までの流れの改善点が一目で分かるようにまとめておけば、将来類似の問題が発生した際にも参考にできます。 -
根本原因分析(RCA)の代表的な手法

前述した通り、根本原因分析(RCA)にはさまざまな手法があります。手法ごとに強みが異なるので、分析を行う際は問題に適した手法を選ぶことが大切です。
ここからは、根本原因分析の代表的な手法を6つご紹介します。5why分析(なぜなぜ分析)
5why分析(なぜなぜ分析)は「なぜ」を5回繰り返すことで、問題の本質的な原因を突き止める手法です。トヨタ自動車が提唱したフレームワークで、製造現場を中心に多くの業界・業種で用いられています。シンプルながら、根本原因を特定しやすいのが特徴です。
例えば、定期的にシステム障害が起こる場合、以下のように「なぜ」を繰り返して分析を行います。
1.なぜシステム障害が起こるのか?:定期メンテナンスを実施できていない
2.なぜ定期メンテナンスを実施できていないのか?:メンテナンスのスケジュールを管理できていない
3.なぜスケジュールを管理できていないのか?:管理者にスケジュールを策定する余裕がない
4.なぜ管理者のスケジュールに余裕がないのか?:人材不足に陥っている
5.なぜ人材不足なのか?:人材確保と業務効率化のための施策を行えていない
この場合、採用の許可や外部委託による人材確保、システム導入による業務効率化によって、問題の解決を図れます。フィッシュボーンチャート(特性要因図)
フィッシュボーンチャートとは、ある結果と、それに関係するさまざまな要因を1つの図にまとめて整理する手法です。図が魚の骨のような見た目になることから、この名前がついています。
フィッシュボーンチャートでは、以下の手順で根本原因の分析を進めます。
1.解決したい問題を明確にする
2.その問題に関連しそうな要因を思いつく限り書き出す
3.書き出した各要因について、さらに掘り下げて原因を洗い出す
4.洗い出した中から、問題に最も大きく影響している原因を特定する
考えられる要因を細分化して、全て図にまとめることで、直感的に状況を把握しやすいのが特徴です。チーム内で問題を共有する際にも適しています。フォールトツリー分析
フォールトツリー分析とは、望ましくない事象をトップ事象として特定し、そこから階層的なツリー構造で要因を整理して、根本原因を特定する手法です。「故障の木解析」とも呼ばれます。
この手法の特徴は「AND(◯と△が同時に起こると×が起こる)」や「OR(◯か△のどちらかが起こると×が起こる)」といった論理記号を用いることで、各事象がどのように関係しているのかを把握できることです。
フォールトツリー分析は、以下の流れで分析を行います。
1.トップ事象を決定する
2.トップ事象につながる直接的・間接的な要因を全て洗い出す
3.論理記号を使ってトップ事象と要因(上位事象・中間事象・基本事象)をツリー状につないで図式化する
4.基本事象の発生頻度でレベル分けした上で、トップ事象が発生する確率を割り出し、どのリスクが高いかを見極めるログ分析
ログ分析は、ソフトウェアのログデータを参照し、解析を行うことで、根本原因を特定する手法のことです。
この手法を行えるのは、ソフトウェア上に発生した問題に限定されますが、データに基づいた正確な分析を行うことができます。分析結果を活用すれば、セキュリティ強化にも役立てられるのが特徴です。また、ログのモニタリングにより、異常や不具合を検知することもできます。パレート図
パレート図とは、棒グラフと折れ線グラフを組み合わせた図表で、問題の要因を可視化し、優先的に対処すべき項目を明確にする手法です。
この手法は、イタリアの経済学者ヴィルフレド・パレートが提唱した「パレートの法則」に基づいています。パレートの法則とは「全体の成果の80%は、わずか20%の原因から生じている」という考え方で、少数の重要要因に注目することで効率的な改善が可能になるというものです。
パレート図では、定量的なデータ(件数や影響度など)を分析対象とし、以下の図表を作成します。
・棒グラフの縦軸:各原因の発生件数や影響度
・棒グラフの横軸:原因や問題の種類
・折れ線グラフ:累積比率(それぞれの原因が全体に対して占める割合)
このように図表として整理することで、全体への影響が特に大きい「重要な少数」の要因を特定できるため、問題解決のための優先順位が付けやすくなります。散布図
散布図とは、2つの変数を組み合わせたデータを点で表してグラフ化し、両者の関係を可視化する手法です。
散布図を使用すれば、そのデータにおいて、二つの要素に関連性があるのかが一目で把握できます。特に、原因が複数考えられるような問題において、どの要因が最も強く影響しているかを見極めるのに役立ちます。
例えば製造業なら、縦軸を不良率、横軸を加工温度にすると、二つの関係性が視覚化され、加工温度の高さや低さが不良率に影響するかを判断することが可能です。 -
根本原因分析(RCA)を実施する際のポイント
最後に根本原因分析(RCA)を実施する際のポイントを解説します。
人ではなく仕組みの欠陥を探す
根本原因分析を行う際は「人」ではなく「仕組みの欠陥」に目を向けることが重要です。
トラブルが発生した際、ついつい「誰に原因の責任があるのか」を追求してしまいがちです。しかし、ほとんどの場合、責任の所在を追及するだけでは、表面的な対応にとどまり、根本的な解決には至りません。
トラブルの再発を防ぐには、ヒューマンエラーの背景にある仕組みやルールの欠陥に着目し、見直すことが重要です。幅広くデータを収集する
根本原因分析をする際は、幅広くデータを収集することも欠かせません。
トラブルが発生すると、どうしても最初に判明した原因に着目してしまいやすいです。しかし、先入観がある状態で根本原因分析を行うと、分析結果に偏りが出るリスクが高くなります。
前述した通り、問題の根本原因は一つとは限らず、複数の要因が重なっている場合も少なくありません。また、逆に一つの根本原因が、複数のトラブルの要因となっている可能性もあります。
現時点で把握できていない原因がある可能性を常に考慮し、幅広くデータを収集して、客観的な分析を行うことが大切です。関係者を巻き込み多様な視点を取り入れる
関係者を巻き込み、多様な視点を取り入れることも、根本原因分析を実施する際の重要なポイントです。
分析をするメンバーが限定的だと、無意識のうちに分析に偏りが出やすくなります。客観的な分析を行うには、複数の関係者の協力を得て、ヒアリングや意見交換を行うことが欠かせません。
加えて、メンバーから多様な視点を引き出すためには、トラブルへの関与度に関わらず、誰もが自由に意見を出せる環境を作ることが大切です。 -
まとめ
トラブルが発生した場合、直接原因と根本原因があり、根本原因を解決しないことには、同様のトラブルが再発するリスクが高くなります。トラブルを未然に防ぐためには、根本原因を特定することが重要です。本記事を参考にして、根本原因分析を行い、トラブルの背景に潜んでいる本質的な原因を解明して、適切な対応策を立てましょう。
問題の根本原因の解明を効率化したいなら、ITサービス管理ツールの導入もおすすめです。ITサービス管理ツール「SmartStage ServiceDesk」は、ユーザーの問い合わせの中から、原因の解明が必要なインシデントを問題管理プロセスに引き継ぎ、根本原因の解明をサポートします。立案した対応策はナレッジとして蓄積されるため、再発防止にも効果的です。その他の機能もお試しいただける「完全版トライアル」をご用意しているので、お気軽にお問い合わせください。