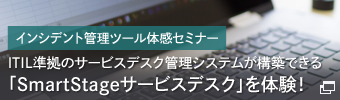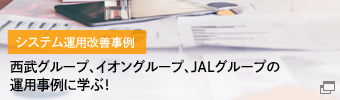![]() コラム
コラム
SRE(Site Reliability Engineering)とは? 注目されている理由や活用する際のポイントを解説
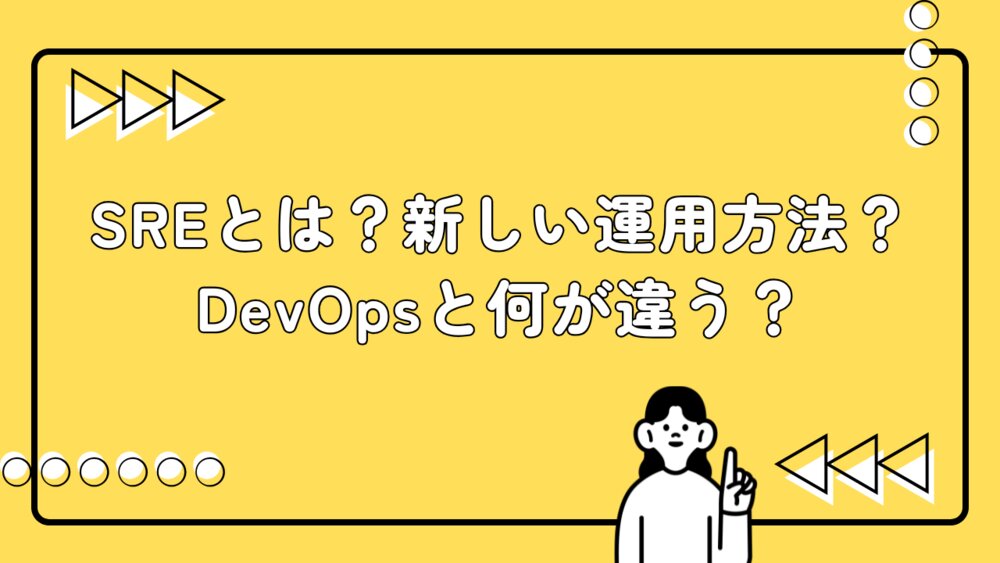
目次
-
SRE(Site Reliability Engineering)とは、システム管理とサービス開発・運用に関する概念です。近年SREを導入する企業が増えていますが、導入するとどのようなメリットが得られるのでしょうか。
本記事では、SREの概要や導入のメリット、活用のこつと注意点などを解説します。SREの導入を検討している方は、本記事を参考にしてSREへの理解を深めましょう。 -
SREとは?

SREとは、Google社が提唱したシステム管理とサービス開発・運用に関する概念です。Site Reliability Engineeringの略称で、日本語では「サイト信頼性エンジニアリング」と訳されます。
SREの目的は、ソフトウェア・エンジニアリングの活用により、人による対応を減らし、自動化・プログラミングによって、インフラの信頼性を向上させることです。ここでいう「インフラの信頼性」とは、一定条件下でシステムが問題なく動作し、安定してサービスを提供し続けられる状態を指します。
従来のシステム運用では、開発チームと運用チームがそれぞれ独立して業務を行っていました。そのため、開発側は新機能の開発やスピーディなリリースを重視する一方で、運用側はシステムの安定した運用を重視しており、両者にギャップが生じやすい状況でした。SREを導入することで、開発チームと運用チームが連携してシステムを運用できるようになり、両者間に生じるギャップを埋めやすくなります。 -
SREとDevOpsの違いとは?
「DevOps」もSREと同じく、効率の良いシステム運用を行う概念です。SREの導入を検討しているのなら、これらにどのような違いがあるのかも、理解しておきましょう。
ヘルプデスク(FAQ)機能
DevOpsとは、開発(Development)と運用(Operations)を組み合わせた造語です。明確な定義は存在しないものの、開発チームと運用チームが連携し、サービスやアプリケーションの開発・運用を効率化するための考え方を指します。
前述した通り、システム運用において、開発チームと運用チームにはギャップが生じやすいです。両者の意見や目的が衝突し、システム運用がスムーズに行えないケースも少なくありません。
DevOpsは、開発チームと運用チームの一体化により、さらに価値のあるアプリケーションやシステムを継続的に開発・提供するだけでなく、ビジネス全体の価値向上や組織文化の変革を含めた広い概念です。DevOpsの手法には、継続的インテグレーション(CI)や継続的デリバリー(CD)などがあります。SREはDevOpsを実現する一つのアプローチ
SREとDevOpsはしばしば混同されることがありますが、SREを提唱したGoogleは、両者の関係を「class SRE implements DevOps」と表現しています。これは「SREはDevOpsを実装する」という意味です。すなわちSREは、DevOpsの概念を具体的に実践する方法だといえます。
前述の通り、SREはソフトウェア・エンジニアリングによって運用課題を解決するアプローチです。課題解決のために、エラーバジェットなど独自の実践方法が用いられます。 -
なぜ今、SREが注目されているのか? 導入のメリット

今SREが注目されているのは、その導入によってシステムの開発・運用にさまざまなメリットがもたらされるためです。ここからは、SREを導入することで具体的にどのようなメリットが得られるのかを解説します。
社会の変化に強くなる
SRE導入のメリットの一つは、社会の変化に強くなることです。
現代では、事業環境が目まぐるしく変化しており、それに伴いシステム運用にも迅速かつ柔軟な対応が求められています。また、インフラのクラウド化や分散化なども進んでおり、システムの開発・運用には、これまで以上の高い対応力が必要不可欠です。そのため、社会の変化に的確に対応することは、システム運用における重要な課題となっています。
SREを導入すれば、柔軟なシステム運用ができるようになり、変化に対してスピーディかつ安定した対応の実現が可能です。システムの安定稼働が可能になる
システムの安定稼働を実現できることも、SREを導入する大きなメリットの一つです。
SREを導入すると、システム運用のさまざまな場面で作業の自動化が進み、人による対応によって発生するミスや不具合を防止できます。また、SLO(Service Level Objective)やSLI(Service Level Indicator)などの指標を活用することにより、システムの状態を常に可視化して管理できるようになり、万が一障害が発生した場合でも、その影響を最小限に抑えることが可能です。SLOやSLIの詳細については、後ほど解説します。
さらに、SREを導入すれば、インシデント対応の標準化も進められます。異常が発生した際の初動対応も、より迅速かつ的確に行えるようになるでしょう。運用作業を効率化できる
運用作業を効率化できることも、SRE導入によるメリットの一つです。
SREを導入することで、インフラコード(システムインフラの構築をコード化したもの)やシステムモニタリングの自動化が可能になります。これにより、担当者の作業負担が軽減され、空いた時間を他の重要な業務に充てることが可能です。
人手に依存しない仕組みを構築し、運用プロセスの改善を行うことで、さらなる効率化も期待できます。また、自動化によって作業の再現性が向上するので、品質の安定性も高まるでしょう。業務の属人化を防げる
SREの導入は、業務の属人化を防ぐ上でも有効です。
システム運用に必要な作業が属人化すると、担当者の不在時や異動、退職などにより、ビジネスに大きな影響を及ぼす恐れがあります。SREの概念に則り、自動化できる作業に関しては自動化し、自動化が難しい作業はナレッジを文書化して共有することで、属人化を防ぐことが可能です。
特定の担当者に依存している状況を改善できれば、予期せぬトラブルが発生するリスクを低減できます。加えて、作業品質を一定に保てるようになるので、品質のばらつきの解消にもつながるでしょう。属人化を防ぐには、誰もが理解できる形で、運用や改善に関するノウハウやプロセスを明文化することが必要不可欠です。トラブル発生時の対応工数を減らせる
トラブル発生時の対応工数を減らせることも、SRE導入によるメリットです。
トラブル時には迅速な対応が求められますが、対応工数が多いほど時間がかかり、被害が拡大するリスクも高まります。例えば、SREを導入してアラートを最適化すれば、本当に対応が必要なものだけに絞り込むことができ、無駄な対応を削減して、担当者の負荷軽減が可能です。
また、エラーバジェットの活用により、リスク管理を行いながら、変化に応じた適切な対応を取ることができます。さらに、システム障害時の対応手順の整備や自動復旧機能の導入によって、トラブル発生時にもスピーディかつ正確に対応できる体制を構築できます。 -
SREにおける4つの重要な指標
SREを実践して、サービスの品質を評価するためには、指標を用いた測定が欠かせません。ここからは、SREにおける4つの重要な指標について解説します。
SLO
SLOは、Service Level Objectiveの略称で、「サービスレベル目標」と呼ばれます。後述するSLIで定義された指標に対して、達成すべき目標値を設定したものです。
たとえば、可用性(システムが正常に継続稼働できる時間の割合)や、レスポンスタイム(リクエストに応答するまでの時間)、エラー率(リクエスト全体に対するエラーの割合)といったサービスの品質に関わる指標に対し、目標値を設定します。SLOは、ビジネスの要件やユーザーのニーズに応じて設定するのが一般的です。
例えば、可用性でSLOを99.0%以上とした場合、「100時間のうち、システムが正常に稼働する時間が99.0時間以上」が、達成すべき目標となります。SLOを設定する際は、理想的な数値ではなく、ユーザーが不満を感じない最低限の数値を目標とすることが推奨されています。
SLOは、サービスの信頼性を向上させるための重要な目標値です。また、エラーバジェットと組み合わせることで、障害やエラーの許容度を可視化し、信頼性とリリース頻度のバランスを見極めるための判断材料にもなります。SLI
SLIは、Service Level Indicatorの略称で、「サービスレベル指標」と呼ばれます。一般的にはSLIとして設定されるのは、以下の項目です。
可用性:システムが正常に継続稼働できる時間の割合
レスポンスタイム:リクエストに応答するまでの時間
エラー率:リクエスト全体に対するエラーの割合
スループット:一定時間当たりに送信可能なデータ量
上記のように、SLIは実際に計測される数値を指標とし、前述したSLOを評価するための基準となります。どのような項目を指標とするかは、サービスの特性などを考慮して、設定しなければなりません。
SLIを選定する際は、指標の数に注意することが重要です。複数の指標を選定すると、多角的にサービスを分析できますが、数が多すぎると、運用や分析が複雑化します。正確で価値のある分析を行うには、後述するCUJを用いて、ユーザー視点で適切な指標を絞り込むことが大切です。
また、SLIを継続的にモニタリングすることで、システムの信頼性やユーザー満足度の向上につながります。SLA
SLAは、Service Level Agreementの略称で、「サービスレベル契約」と呼ばれます。サービスの提供者と顧客が交わすサービス品質に関する契約を数値化したものです。一般的にSLOとSLIを基に信頼性を担保できる基準を明確に定め、書面で締結します。
SLAで設定した数値を満たせなかった場合、サービス提供者にペナルティが科せられるケースが多いです。例えば、可用性のSLAを「99.0%以上」と定めていたにもかかわらず、100時間のうち、システムが正常に稼働する時間が99.0時間以上を下回った場合は、顧客に対して返金などの補償が発生します。
SLAは、顧客との間で結んだ契約条件の一部と見なされるので、法的拘束力を持つ場合もあります。一方で、SLAを満たしている限り、たとえ顧客が不満を感じたとしても、契約違反とは見なされないのが一般的です。CUJ
CUJとは、Critical User Journeyの略称です。顧客がサービスを認知して購買行動に至るまでの一連の流れを「カスタマージャーニー」と呼びますが、CUJはこのカスタマージャーニーの中でも、特にビジネス上の価値が高く、顧客にとって重要となる操作や体験のプロセスに注目したものを指します。
例えば、ECサイトにおいては、「ログイン」「商品検索」「カート投入」「決済」が、代表的なCUJです。各工程における顧客の満足度を測定・分析し、適切な改善を行うことで、顧客満足度を向上させることができます。
また、前述した通り、CUJはSLIの項目を絞り込む際の参考となります。さらに、アラート設計の最適化にも不可欠な要素です。
分析をする際は、事前準備として、目的を明確化した上で、顧客のペルソナの設定、行動データの収集、顧客の分類などを行います。その上で、顧客と自社のタッチポイント(接点)や、その際の顧客の感情の動きや反応などを整理し、ユーザー体験に大きな影響を及ぼすプロセスや、ビジネスの成果に直結するプロセスを評価します。
CUJを考慮したシステム開発・運用は、ユーザーの期待に応える信頼性の高いシステムを実現する上で欠かせません。 -
SREエンジニアが担う役割とは?

SREエンジニアは、文字通りSREに携わるエンジニアのことです。SREエンジニアは、どのような役割を担っているのでしょうか。
SREエンジニアに求められるスキルや経験、具体的な担当業務などを解説します。必要となるスキルや経験
SREエンジニアには、開発・運用の両面に関する知識やスキル、実務経験が求められます。
開発面においては、Python・Goなどを代表とするプログラミング言語の知識や、コーディングスキル、リポジトリやCIといった管理ツールを活用するスキルなどが必要です。運用面において必要不可欠なインフラやネットワーク、クラウド、セキュリティなどに関する幅広い知識も求められます。加えて、SRE業務に欠かせないモニタリングツールやCI・CDを活用した実務経験があることも望ましいです。
また、SREエンジニアは、開発チームと運用チームの橋渡し的な存在です。両者のスムーズな連携を支援するために、高いコミュニケーションスキルも求められるでしょう。従来の運用エンジニアとの違い
従来のエンジニアと比べて、SREエンジニアは手作業よりも自動化を重視し、再現性を高められるように運用を行います。
また、一般的なエンジニアと比べるとコードを書くことが多く、エンジニアリングの比重が高いことも、SREエンジニアの特徴です。トラブル発生時の対応も行いますが、それに加えて、リリース前のエラーやバグの解消によってトラブルを未然に防ぐ他、発生したトラブルの再発防止に向けて、改善にも注力することも求められます。具体的な担当業務
SREエンジニアが担当する具体的な業務には、以下のようなものがあります。
安定性の高いシステムの開発・運用
開発工程やデプロイの自動化
障害の早期検知と対応(モニタリング、アラート設計、オンコール対応など)
パフォーマンスチューニング
信頼性向上・改善のための施策提案
開発業務で必要な仕組みの構築・提供 -
SREをうまく活用するためのこつと注意点
最後にSREをうまく活用するためのこつや注意点を解説します。
高過ぎる目標値を設定しないようにする
SREをうまく活用するためには、高すぎる目標値を設定しないようにしましょう。
SLOを設定する際、例えば可用性が100%というような目標値を設定する必要はありません。ユーザーが不満を感じないサービスレベルを見極め、現実的な数値を設定することが大切です。SLOを決定する際は、サービスの重要度や提供コストとのバランスを考慮し、達成可能な適切な数値を設定しましょう。
また、エラーバジェットを活用し、サービスの変更やリリースに伴うリスクを適切に管理することも重要です。チームだけでなく組織全体で取り組む
SREを導入する際は、チームだけでなく組織全体で取り組むことがポイントです。
現代のビジネスにおいて、ITはあらゆる業務の基盤となっており、システム開発や運用の体制を見直すことは、他部門にも影響を及ぼします。そのため、SREを効果的に機能させるには、現場のチームだけでなく、マネジメント層を含めた全社的な理解と協力が必要不可欠です。加えて、トラブル共有やナレッジ管理の文化を構築し、組織全体に浸透させることで、SREの効果を高められます。
組織全体でSREの導入を支えることにより、開発・運用チームの孤立を防ぎ、横断的な連携と継続的な改善が可能な体制を築くことが可能です。一度やって終わりにせず、継続する
SREをうまく活用するには、一度実施して終わりにせず、継続的に取り組んでいくことが重要です。
定期的なレビューや、発生したトラブルなどの事後検証(ポストモーテム)を行い、結果を改善に生かすことは、信頼性向上につながります。顧客満足度の高い信頼性を構築するには、一貫した取り組みの積み重ねが欠かせません。
スモールスタートで始め、成果を可視化しながら、パフォーマンスを向上させましょう。 -
まとめ
Googleが提唱した信頼性向上のための運用手法であるSREは、開発と運用の連携を通じて、システムの信頼性向上と柔軟なシステム拡張性の両立を実現します。SREを導入する際は、ご紹介したこつや注意点を踏まえ、現実的な目標値を設定しながら、段階的に拡大して、小さな成功を積み重ねましょう。
ITにおける管理プロセスを効率化したいなら、ITサービス管理ツール「SmartStage ServiceDesk」の導入もご検討ください。ITILに準拠した管理プロセスを短期間で無理なく導入することで、ITサービスデスク業務を改善し、運用コスト削減にも貢献します。カスタマイズが柔軟に行えるため、自社に合った運用が可能です。全機能をお試しいただける「完全版トライアル」もご用意しているので、お気軽にお問い合せください。