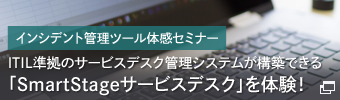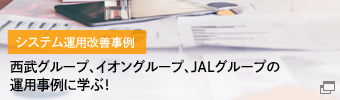![]() コラム
コラム
CSI(継続的サービス改善)とはどのようなもの? 目的や重要性に加え導入のポイントも解説
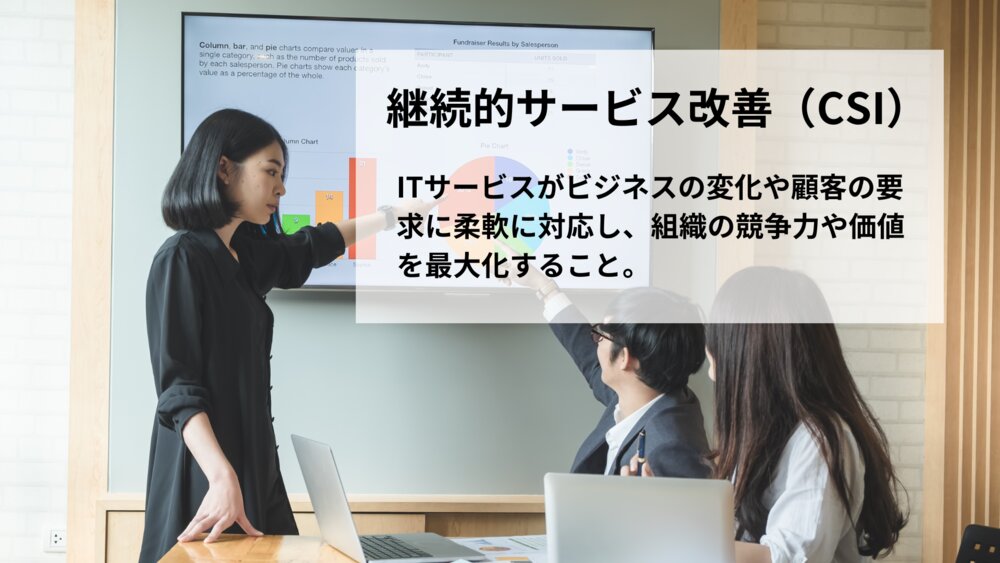
-
現代社会においてITは企業の成長や存続に不可欠といっても過言ではないでしょう。そうした中でCSI(継続的サービス改善)は欠かせません。
CSIとはICTサービスの品質および顧客満足度の向上を目指す重要なプロセスです。ITサービスマネジメントにおいてCSIは変化するビジネスニーズに対応し、サービスの価値を継続してアップさせる役割があります。
本記事ではCSIの概要を確認した上で、CSIについて効果や実施プロセス、成功事例、導入のポイントなどを解説します。 -
CSI(継続的サービス改善)とは?

CSIとはContinual Service Improvementの略で、日本語では継続的サービス改善といいます。PDCAサイクルに基づいて、ICTサービスおよびICTサービスに関連する活動を継続的に改善するプロセスを指します。CSIは、ITサービスマネジメント(ITSM)におけるベストプラクティス(成功事例)を5つのカテゴリに分類してまとめた書籍群「ITIL V3」のプロセスに含まれています。なおITILとはサービスの設計から運用、さらには改善までをサイクルとしたフレームワークです。CSIは変化が激しいビジネスニーズに対応し、サービスの価値を継続的に高めるために重要とされています。
CSIの目的
CSIの目的は変化する市場や競合他社のサービスの進化を把握しつつ、サービスの顧客満足度を高めたり水準を維持したりすることです。
CSIの重要性
CSIは変化に対応するためのプロセスとして必要不可欠です。
デジタル技術の急速な進歩や顧客ニーズの変化、新たな規制の導入などによって、ICTサービスは日々進化することが求められています。
CSIが効果的に実施されることによって、ITサービスの価値は高まり、ビジネス目標を達成できるでしょう。また従業員がサービスの改善を常に意識するようになれば、組織のボトムアップにつなげることも可能です。 -
CSIとItILの関連性
前述の通り、ITILはITサービスマネジメントにおけるベストプラクティスをまとめた書籍群のことです。ITILはサービス・ストラテジ、サービス・デザイン、サービス・トランジション、サービス・オペレーション、継続的なサービス改善の5つのカテゴリに分類されています。
ITIL4ではCSIの概念は発展的なものとして扱われており、継続的改善として組み込まれています。
つまりCSIはITILのフレームワークにおいてサービス改善の中核を担っており、ITILの他のフェーズと連携し合うことでサービスライフサイクル全体で効果を表します。 -
CSIによる効果とは?
CSIの実施を検討している企業の担当者の多くが、CSIによってどのような効果を得られるのか気になるところでしょう。
CSIによる効果として、以下の7つが挙げられます。
1.業務におけるプロセスの効率化
2.リスク管理の向上
3.ITサービスの質向上
4.顧客満足度・ロイヤリティのアップ
5.投資対効果の促進とコスト削減
6.イノベーションの活性化
7.競争優位性の打ち立て
それぞれ確認していきましょう。それぞれ確認していきましょう。
業務におけるプロセスの効率化
CSIを実施することで、必要ない業務や重複した業務を洗い出せます。従来のプロセスの一部を削減・自動化すれば従業員のリソースを確保でき、新たに独自のビジネスや質の高いサービスを生み出すこともできます。
リスク管理の向上
CSIを実施することで、今後起こり得るトラブルを予測できます。トラブルが起こらないように対策しておけるので、万が一のときにもビジネスへの影響を最小限に抑えられるでしょう。昨今増えている災害に備えた復旧計画の改善にもつながります。
ITサービスの質向上
CSIによって改善点が洗い出されるため、品質が向上します。またサービスが均一化されるので、自社への信頼性向上にもつながるでしょう。
顧客満足度・ロイヤリティのアップ
CSIによって顧客のニーズをいち早く掴めるようになり、顧客満足度をアップできます。
例えばカスタマーサポートの改善やサービスレベル合意(SLA)の達成率を向上させるといった改善計画によって、顧客と長期的な関係を構築できます。顧客のロイヤリティが高まれば、長期的な利益化が見込めるでしょう。投資対効果の促進とコスト削減
CSIで業務プロセスが効率化できれば、サービスの運用にかかるコストを削減できます。サービスが改善すればトラブルに対応するための手間やコストも減る他、品質向上による投資対効果(ROI)の最大化にもつながるでしょう。
運用コストの無駄を省くことで、限られたリソースをより有益なものに使うことも可能です。イノベーションの活性化
継続的なサービス改善の習慣が当たり前になると、創業当初からの伝統や慣習にこだわっていた企業においても変化が生まれ、市場の変化に柔軟に対応できるようになります。
また消費者の声や時代のニーズをくみ取ったビジネスを展開することで、変化が激しい現代社会においても安定した利益を得られるでしょう。
さらに、新しい分野に挑戦する企業の姿勢は若手社員からも高く評価され、人材の定着につながるでしょう。競争優位性の打ち立て
CSIを実施することで継続したサービス改善を行えるため、顧客により高い価値の提供が可能となり、競争優位性を高められます。
市場シェアが拡大すれば新規顧客を獲得できるだけでなく、自社のブランド価値を維持できるため既存顧客の流失を防ぐ効果も得られます。
またこうした成果を生かして業界内でリーダーシップを発揮することで、持続可能な成長の実現も期待できるでしょう。 -
CSIにおけるPDCAの役割
CSIはPDCAサイクルを中心に行います。
PDCAはPlan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)の頭文字を取った言葉で、これら4つのプロセスを繰り返して改善を進めるフレームワークです。
PDCAサイクルはPlanからスタートしているものの、Check(評価)から始めるのが成功の秘訣です。次の章で解説するCSIの実施プロセスにおいてもCheck(評価)から始まっています。
またPDCAは一回限りで終わらせるのではなく、成果が出るまで何度も繰り返すことが重要です -
CSIの実施プロセス

CSIを実施する際はプロセスに従うことが大切です。プロセスに従うことで最大限の成果を得られるでしょう。
CSIの実施は以下の7つのステップで行います。このステップはITILフレームワークの中核となっているプロセスであり、継続的な改善を実行する指針となります。
1.測定対象を定義する
2.測定可能な項目を定義する
3.データを収集する
4.データを処理する
5.データを分析する
6.情報を提示し活用する
7.是正措置を実施する
それぞれ確認しましょう。1.測定対象を定義する
まずは測定対象を定義しましょう。サービス改善を行うためには、現在のサービスを分析して、企業が掲げる目標を達成できているのかを確認する必要があります。
測定対象を定義するには、以下の内容を確認しましょう。
● サービスレベル合意(SLA)はどのくらい達成されているのか
● 同業のベストプラクティスと比べてどのように違うか
● 顧客満足度はどのくらい達成されているか
● インシデントにはどのような傾向があるか2.測定可能な項目を定義する
測定対象を定義したら、改善状況を把握するための基準を定義します。以下は、主な測定基準です。
● 技術的測定基準:サービスを提供しているシステムが稼働している時間
● プロセス測定基準:インシデント発生から解決までにかかった時間、変更が成功する確率
● サービス測定基準:サービスの可用性、満足度
測定基準を決めておけば、改善を行う上で途中経過を確認できる他、改善活動を客観的に表かできるようになります。3.データを収集する
測定対象に関するデータ収集を行います。データを収集する際は責任者、収集方法、頻度を事前に決めておくと、効率的に進められます。
データ収集を実施する際は、スムーズに行うためにも次の点に注意してください。
● プライバシーへの配慮、セキュリティ対策ができているか
● 信ぴょう性の高いデータか
● 情報収集の方法は適切か
● リアルタイムデータを収集する可能性があるか
またデータ収集において自動化ツールを活用することでより効率的に行えます。4.データを処理する
収集したデータを分析できるように形式を統一しましょう。データクレンジング、フォーマット変更などを行って、分析できるように準備してください。
データの処理では主に以下のタスクがあります。これらのタスクを行うことで、データ分析基盤の構築が整います。
● 重複データを消す
● 異常値の検出および対処
● 欠損値の処理
● データの規格化5.データを分析する
データ分析では、トレンド分析やベンチマーキングなどを使って、改善すべき課題の特定を行います。
また分析結果を基に目標の達成度や問題の原因、事業活動への影響などを分析します。分析する際は、次の手法を取り入れるのが一般的です。
● 時系列分析
● ルート原因分析
● 相関分析
● 予測モデリング6.情報を提示し活用する
データ分析が完了したら、分析結果を資料にまとめて関係者と共有します。
資料を作成する際は、以下のポイントを押さえておくと伝わりやすい内容になります。
● グラフや表、イラストを使って視覚的に分かりやすくする
● 情報の過不足がないか、粒度に問題がないか確認する
● 太字やマーカーを引いてポイントが分かるようにする
● 分析結果を基にした具体的な行動計画を盛り込む7.是正措置を実施する
関係者で話し合い、行動計画が決まったら、改善に向けてアクションを起こします。改善計画を実行に移したらそれで終わりにせず、結果を評価して最終目標に向けたさらなる改善につなげましょう。
改善計画を実行する際は以下の点に注意し、継続的な改善を行うことが大切です。
● 目標値と期限を設けて小まめに結果を評価する
● 改善計画の責任者と実行役を決め、業務を分担する
● 小まめな進捗報告を行い、定期的に評価を行う
● 不測の事態やトラブルにはスピーディーな対応を心掛ける -
CSIの成功事例
CSIではまず測定することが大切です。ここで、測定からスタートしたことで業務改善が図れたA社の営業部門の事例をご紹介します。
A社の営業部門では顧客管理、商談管理、案件の進捗管理、売上管理といった業務の一元化を目指してSFA(営業支援)とCRM(顧客管理)システムを導入しました。同社では、各営業社員が表計算ソフトを利用して個別に管理していましたが、業務生産性アップを目的に導入が実現。
同社は入力業務・処理に要する時間を計測して、労働時間と人件費に換算し、コストを比較しました。さらに一元的な実績管理に基づいて分析した予測、および営業社員の経験に基づいた属人的な予測の正確性を比較。両者を比べてみたところ、コスト面においても予測の正確性においても、SFA/CRMシステムが優位であることが分かりました。A社は上記の結果を共有し、SFA/CRMシステムの利用を社員に定着させたそうです。
SFA/CRMシステムを使用するに当たり、全員が効果的に活用できるようシステムの使い方の見直しも定期的に行いました。
こうした一連の取り組みの結果、A社は正確な予測による売上目標・事業計画の立案が可能になり、業務の生産性もアップしたそうです。 -
CSIの導入ポイント

CSIを実施すればサービスが改善され、自社の利益の長期的な向上につなげられます。しかしCSIは単に導入すれば良いわけではなく、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
CSIの取り組みを成功させるには、従業員間で協力して問題を解決するという考え方を社内において根付かせることが重要です。そのためのポイントとして主に以下が挙げられます。
● 達成しやすい目標を定めて、取り組みやすい問題から手を付ける
● 入手可能なデータで測定できるKPIを設定する
● 改善点を見つけたら関係者へ共有する
とはいえ、CSIを実施するに当たって急速に変化しているITインフラを整備できないという課題に直面したり、人材不足からシステム管理が難しかったりするケースもあります。こうした場合はツールの活用によって、CSIを継続的に実施しやすくなります。 -
まとめ
CSIはITサービスマネジメントのフレームワークであるITILにおいて重要な概念です。自社が提供するITサービスやそれを支えるプロセスなどを継続的に評価し、改善するプロセスです。
CSIを自社で実施するには知識やスキルを有する人材が必要となります。また実行に移すには手間も時間も要します。そのようなときは、ツールを導入するのがおすすめです。
Smart Stageは、ITIL®に準拠したサービスで、さまざまなプロセス管理とデータ管理を実現できます。CSIを実施してサービス改善を効率的に進めたい方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。